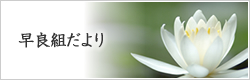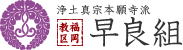- トップページ

- 報恩講・永代経



 「早良組蝋燭講」は、世の中が混沌とした明治維新の時代に、早良郡内の御同行が「親様の御前に報謝の一灯なりとも捧げたい」との念願をもって、明治11年7月に創立されました。翌年には本願寺に申請して認可されています。
「早良組蝋燭講」は、世の中が混沌とした明治維新の時代に、早良郡内の御同行が「親様の御前に報謝の一灯なりとも捧げたい」との念願をもって、明治11年7月に創立されました。翌年には本願寺に申請して認可されています。
その当時、講員一人につき二厘宛て報謝のもとに、筑前名産の甘木蝋燭を手にして徒歩で京都の本願寺へお供えに行かれたそうです。このことが明如上人(本願寺第21代門主)の御心に留まり、明治14年5月24日に、早良組蝋燭講に対し御消息(お手紙)が下付されました。
以来毎月13日に、早良組内の御法中(僧侶)の御出勤を仰ぎ、お勤めされています。また、毎年春秋の2回(3月13日と9月13日)は浄土三部経を拝読しております。